- ホーム
- Webオープンキャンパス
- 学生募集、入試情報
オープンキャンパス - 大学案内
- 大学案内について
- 大学概要
- 学生サポート
- 進路支援
- 健康支援
- 付属図書館
- 地域連携
- ボランティア活動
- あやな会
- 付属みどり野幼稚園
- インフォメーション
- 学科・専攻科
- 学科・専攻科について
- 経営情報学科
- 食物栄養学科
- 幼児教育学科
- 健康福祉学科
- 専攻科食物栄養専攻
- キャンパスライフ
- キャリア・就職
- 公開講座
- 訪問者別メニュー
- お問い合わせ
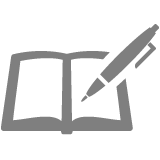 学習内容・成果
学習内容・成果| 1年次 | ||
|---|---|---|
| 教養 科目 |
教養科目 |
|
| 外国語科目 |
|
|
| 演習 | 教養演習Ⅰ・Ⅱ | |
| 専門 科目 |
経済 ・ 経営科目 |
|
| 会計科目 |
|
|
| ビジネス実務 ・ キャリア科目 |
|
|
| 情報科目 |
|
|
| 図書館司書課程 |
|
|
| 2年次 | ||
|---|---|---|
| 教養科目 |
|
|
| 専門 科目 |
経済 ・ 経営科目 |
|
| 会計科目 |
|
|
| ビジネス実務 ・ キャリア科目 |
|
|
| 情報科目 |
|
|
| 演習 | 専門演習Ⅰ・Ⅱ | |
| 図書館司書課程 |
|
|
2年間の集大成として学生自ら研究テーマを設定し、自ら考え、行動するという能動的な学習を行い、
その成果を演習報告書にまとめます。
| 指導教員 | 班 | テーマ |
|---|---|---|
| 東野 善男 | 1 | 古本市で子どもの来場者を増やすにはどのような工夫が必要か |
| 2 | 二次元の推し活はどのように経済効果をもたらすのか | |
| 3 | なぜハローキティは今も愛されるのか | |
| 4 | K-POP第4世代アイドルが活躍したのはなぜか | |
| 5 | プロジェクトセカイは課金する人が多いのはなぜか | |
| 6 | ゲストスピーカーによる特別授業の文字起こし | |
| 7 | 女性歌手が歌う女性像はどのように移り変わっていったのか | |
| 小西 孝史 | 8 | Robomasterにおけるライントレースの最適化及び巡回警備型の課題点 |
| 9 | ユーザーインターフェース最適化に関する実証的研究視覚的要素と操作性の相互作用がユーザー体験に与える影響の解析 | |
| 高木 綾子 | 10 | 企業イメージを決定づける色彩効果に関する一考察 |
| 11 | 安易な性格診断による就職活動への弊害 | |
| 12 | リッツカールトンの戦略が一般企業の顧客リピート率向上に与える影響 | |
| 13 | 若者の恋愛意識と少子高齢化の関連についての研究 | |
| 森井泉 仁 | 14 | 「DX導入の現状」を新聞記事から読み解く |
| 15 | 「再生可能エネルギー導入の現状」を新聞記事から読み解く | |
| 16 | 「EV(電気自動車)の現状」を新聞記事から読み解く | |
| 田中 夕香子 | 17 | eスポーツの多面的な効果 ~教育的価値についての考察~ |
| 18 | メタバースの発展について ~映画『サマーウォーズ』OZの世界との比較~ | |
| 19 | ディープフェイクの可能性とリスク~新たな価値創造~ | |
| 20 | デジタル時代におけるスマートフォンリテラシー ~誰にどのように必要か~ | |
| 春名 亮 | 21 | 氷見の中央商店街活性化に向けた課題抽出:震災復興を目指して |
| 22 | AHPを用いたスマートフォン選択の行動に関する調査 | |
| 23 | AHPを用いたお菓子のキャラクターに対する印象の評価 | |
| 24 | 「鬼滅の刃」が爆発的にヒットした要因 | |
| 藤野 裕 | 25 | ディズニーの経営 -独自の経営と新たな問題の解決策- |
| 26 | eスポーツの人気は続くのか | |
| 27 | VRチャットのこれから | |
| 28 | ちいかわーるど | |
| 山下 裕介 | 29 | 自動車の歴史と今後の展望 |
| 30 | 美容の効果について | |
| 山西 宏明 | 31 | ノンアルブーム -ノンアルコール市場の未来- |
| 32 | 3R -地球を守るために私たちができることとはー | |
| 33 | 紙ストローはなぜ流行らないのか | |
| 34 | 持続可能な社会について | |
| 35 | 海洋ごみ問題の解決策 ―日本ができる環境対策について考えるー |
インターンシップとは、「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと」とされ、事前に学生が取り組む課題を設定し、それに基づいて企業や機関において短期間の実習・研修を行う制度のことです。
本学のインターンシッププログラムは産学官の連携により、学生の夏季休暇中に企業や機関での就業体験を行い、事前研修・事後研修を含めると1年生の8月から9月までの期間を利用して実施しています(認定単位は2単位~4単位です)。


環日本海環境センター
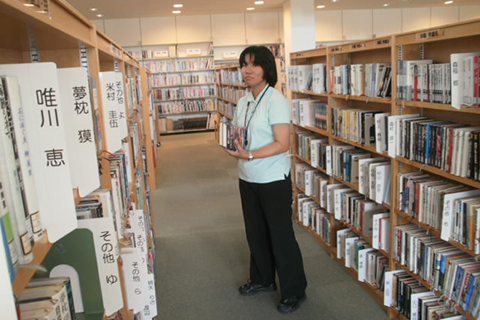

射水市中央図書館
過去3年間のインターンシップ参加率は約95%以上
富山短期大学経営情報学科の特徴である「三位一体」のキャリア教育では、職場研修の「インターンシップ」と「ビジネス実務関連講座」、外部講師による「キャリアデザイン講座・キャリア支援講座」の連携を図って、将来のキャリア設計を行うとともに、就職活動に必要な実践的能力を身につけることを目標としています。「ビジネス実務関連講座」では、企業組織の仕組みや仕事のやり方、またビジネスマナーやビジネス文書の知識を身につけます。「キャリア講座」では、自らの興味・価値観から始まって、自己分析、企業研究、履歴書・エントリーシートの書き方、面接の受け方等の実践的な訓練を行います。これらの知識や考えを職場で実際に試すのが「インターンシップ」に他なりません。
インターンシップは業種、企業、職種、仕事への理解、社会における基本的マナー、コミュニケーション能力などを肌で感じるとともに、その成果を日頃の学習、就職活動、自分の将来などに生かすことができます。このような有益なインターンシップを実施することができますのは、学生を快く受入れてくださいます企業・機関の方々のご理解のお蔭であり、改めて厚くお礼を申し上げます。また、インターンシップ推進協議会並びに事務局のご指導に深く感謝申し上げます。
本学科では、このような貴重な経験を得た学生達が立派にキャリアを形成し、地域社会に貢献してくれることを願い、より一層の努力をする所存でございます。地域社会の企業・機関の皆さまには、今後とも益々のご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。
インターンシップについての問い合わせ
〒930-0193 富山市願海寺水口444 富山短期大学 経営情報学科
求人等についての問い合わせ
〒930-0193 富山市願海寺水口444 富山短期大学 キャリア支援センター
TEL:(076)436-5162
FAX:(076)436-0133
E-Mail:tymc_career@tii.ac.jp